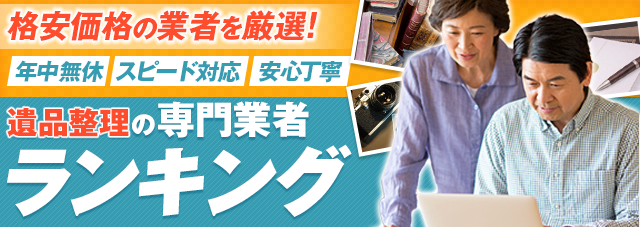相続放棄する場合は要注意
遺品整理をする際に知らないと思わぬトラブルに巻き込まれかねないのが、相続に関する知識です。
血縁者が亡くなったとき、故人の遺産を相続したくないケースもあるでしょう。その場合に法律の知識を持たずに遺品整理をしてしまったら相続放棄ができなくなる可能性があります。というのも、民法では「相続財産の全部または一部を処分したとき、相続放棄が認められない」と定められています。すなわち故人の身の回りの品を片付けたり処分したりすると、その行為が相続する意志があるとみなされてしまうことがあるのです。
しかし一方で、常識の範囲での形見分けは問題ないとされています。ただし「常識の範囲」がクセモノで、資産価値がないと判断していても、市場での価値が見込まれる場合、相続放棄ができなくなることがあります。不安な方は遺産整理をする前に弁護士に相談することをおすすめします。
相続の方法は3通り
それでは相続の方法についてもう少し具体的にご紹介しましょう。
相続には3つの方法があります。1つめは先ほどご紹介した「相続放棄」で、故人の遺産全てを破棄し、相続自体をなかったものにすることを指します。
2つめは「単純承認」で、故人の遺産全てを故人と同じ立場で引き継ぐことを言います。有価証券や土地、お金などはもちろんですが、借金や滞納金といった“負の遺産”も故人が持っていたなら、残らず引き継がなければなりません。そこで問題になるのが、遺品整理を行うと「単純承認」をしたとみなされてしまうケースがあるということです。前の章でもご紹介しましたが、常識範囲内の形見分けは法律上「単純承認」には該当しないといわれているものの、「常識の範囲」の判断が一般人には困難です。遺品整理業者も判断できかねる場合があるため事前に弁護士に相談しておくのがベターでしょう。
最後の「限定承認」は“負の遺産”以外の財産を相続する方法ですが、現実的な相続方法ではありません。
生活保護受給者の遺品整理
もしあなたが生活保護受給者の血縁や、彼らの大家だとしたら、遺品整理には注意が必要です。
もし生活保護を受給中に亡くなってしまったら、葬儀や住居の退去手続きや相続の継続・破棄の決定を、血縁者が行う必要があります。葬儀代は生活保護の中から捻出されることもありますので、最寄りの市役所へ相談してみましょう。
また相続を放棄する場合は家庭裁判所で手続きをしましょう。放棄するということは、遺品のほか退去の権限も無効になるため、市役所が遺品の処理を代行することになります。ただし葬儀や納骨は相続人が行います。逆に相続する場合は、遺品整理のほか葬儀や退去の手続きが必要です。
一方で、ご自身の不動産に生活保護受給者が入居していた場合、相続人と相談をして、いつ退去完了になるかを決めましょう。相続人がいない場合は、市役所が遺品整理と退去を代行することがほとんどです。